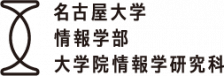秋庭 史典先生 インタビュー 芸術の外を知って芸術をやることの大切さ
聞き手:有田 隆也
(インタビューをしているうちに,アートの現状や今後に関する話が深まっていったので,別記事「今,アートの意味を考える」として掲載しました.ぜひ,この文章を読んだ後に読んでください.)
Q:本日は、まずこの道に入ったきっかけ、あるいは現在の専門に進まれた理由、象徴的な出来事など、そのあと、若い人々に向けてメッセージをいただく、という順でお願いします。
「普通でない」生き方に気づいた
Q:では、きっかけからおうがいします。大学に入って文学部で美学美術史を専攻した、というのが出発点でしょうか。
A:もう少し前のところからお話ししてみたいと思います。小さい頃は特に芸術に興味があって、というわけではなく(絵画教室には通っていましたが)、芸術に関することを仕事にしようとは思っていませんでした。ところが、中学から高校にかけて、周囲にちょっと変わった人たちが現れて、彼らから、普通でない生き方があると教わってしまったのです。その人たちのなかでみなさんがご存じと思われる方をあげると、ついこのあいだまでNHKの大河ドラマに出ておられた俳優さんがそうです。学校は違いますが学年が同じで、彼を知らない人は周囲にいないくらい、面白くて、人を幸せにする方でした。なんて自由な人なんだ、と思いました。彼らを通して、演劇や音楽という生き方があることに気づいてしまったんです [注1]。
その後、大学生になる頃に、岡山大学の近くにある有名なライブハウスを知りました。そこは、写真家・映像作家で、1970年代に雑誌『遊』に寄稿されていたような方がオーナーだったのですが(現在ももちろん精力的に活動を続けておられます)、そのライブハウスに、大学の関係者(哲学、物理学、生物学、地理学などいろんな分野の方がおられました)、近くにお住まいのピアニストの方、マンガを描いていたりお芝居をやっていたりする学生さん、服飾デザイナーやバンド関係など、いろんな方たちが出入りしていて、その方たちの話をうかがっているうちにあらためて感化されてしまったんです。またそこで、1980年代半ば当時若手の美学者だった方々のテキストにも出会っていました。
Q:そのとき、地元のなにかではなくて、たとえば、イギリスのパンクそのものに直接興味を持つというようなことはなかったんですか?
A:それはやはり、田舎だからだと思います。そういう人たちに直に接する機会はありませんから…。それで身近なところにアクセスしていったと。[注2]
Q:(地元の人経由ではなく)直接ほんものに影響を受けるのが重要ということはないですか。
A:はい、そう思います。たまたま影響を受けた地元の人たちの志(こころざし)が高く、世界に目を向けておられたのがよかったのかな、と思います。
「美学」との出会い
Q:では、そうしたきっかけと現在の専門分野とが結びついたのはなぜだったのですか。
A:芸術や文化について考えるには「美学」という学問がある、と知ったのは、山崎正和さんの書かれたものを読んだときでした。山崎正和さん(1934-2020/劇作家)が編集された『近代の芸術論』という本が中央公論「世界の名著」シリーズのなかにあります。当時おそらくどこの高校の図書館にもあったような本です。なぜ山崎正和さんの本に行きあたったかと言うと、それもまたベタでお恥ずかしい話なんですが、高校の現代国語の教科書に、「情報化時代の人間」という山崎先生が書かれたテキストが載っていたのがきっかけです。そこには、今なら小学生でも知っているでしょうけれども、デュシャンの《泉》などが取り上げられていました。そこで山崎先生は当時=1960年代の芸術状況に対してかなり批判的な発言をされています。それがわたしにはすごく面白かったのです。当時は芸術=反体制みたいなイメージがありましたから [注3]。
それで続けて、同じく山崎先生が書かれた『近代の芸術論』の冒頭に置かれた「人生にとって藝術とは何か−近代の藝術論の発見したもの−」を読んでみたんです。それがまた面白かった。そこでは、こんなことが言われていました。
「劇場で行われることは藝術だという因襲的な先入観をあてにして、現実ではたんに軽犯罪にすぎない行為が、そこでは何かしらそれ以上のものになることを空頼みにしているのである。こうした現代藝術家はつねに古い藝術の伝統を破壊することをスローガンにしているのであるが、じつはこのスローガンそのものが、藝術に対する不信というよりはむしろ盲信のうえに立っているといえる。」(山崎正和「人生にとって藝術とは何か」『近代の芸術論(世界の名著81)』中央公論社, 1979, p.12)
制度に守られた反抗、芸術という制度をあて込んだ反芸術というのが、嫌いだったんですね。だからほんとうのあたらしい芸術というのは、いかにも反芸術ぶったところにはないのではないか、と [注4]。それはパンクに心酔して「ぶっ壊せ!」とか言ってる人が、パンクそのものは壊さないのを見て(髪の毛立てて、安全ピン刺してという、いかにもなスタイルで)変だな、と思っていたのと同じです。
いずれにしましても、自分が漠然と興味を持っていた芸術や文化というものと、美学という学問が結びついたのは、このあたりでした。ただ、実際に大学で「美学」を学んでみると、それはまったく想像と違っていて、そこでまた驚くわけですけれども(とても厳しい先生に教わりました。またそのとき、美学と芸術論は違うということも学びました)。
で、そこで初めて、ちゃんと勉強しないとダメだな、と思いました。雰囲気でものを言うのではなく、きちんとした芸術の理論みたいなものがあるのであれば、勉強しないといけないな、と。
Q:そう思うようになったのはいつ頃?
A:けっこう遅いです。大学の2年生とか3年生くらいかと。
Q:で、それを一生の仕事に、と。
A:そうですね。自分にとって(芸術の理論は)難しかったので、そんなにすぐには理解できないだろうな、と。当時さきほどお話ししたライブハウスでいろんな勉強会が行われていたんですけれども、それがまったく理解できない(という以前に、勉強会が夜中に行われるので起きていられない)。そこに置かれている本などを読んでみてもよくわからない。いまから思えば、当時流行りのポストモダン的言説だったのかもしれません…うまく言えないんですけれども、難しいことばを使っているけど、使ってる人もほんとは自分が何言っているかわかってないんじゃないかと思うような議論。それが気持ち悪くて、一回ちゃんと勉強しなければ、と思った次第です。
アート&サイエンス、アート&テクノロジーの方へ
Q: では次に、現在の問題意識に近づいていった経緯について、話していただけますか。
A:当時の先鋭的な若手美学者の方々は、「情報と芸術」という観点からの美学に取り組んでおられて、新宿のNTT/ICCといったところで、最先端のコンピュータ・アート、メディアアートなどについて議論されていました。そうした議論に触れるなかで、芸術という土俵のなかで芸術しか見ていない芸術ではなく、その外を知っていて、そのうえで芸術をやることが大事なのではないか、とますます思うようになりました。それでアート&サイエンスとか、アート&テクノロジーと言われるような領域が目に入ってきたわけです。(それ以前にも原体験としての大阪万博−といっても当時4歳ですが−とか、テクノのおかげでコンピュータを使った音楽を身近に感じるとかいった機会はありましたが。)ただ、サイエンスやテクノロジーとアートについて考えようと思っても、実際にそうしたことを研究しておられる方と交流する機会もそれほどなかったわけです[注5]。
したがいまして、いちばん大きかったのは、2000年に名古屋大学(当時は「人間情報学研究科」)へ赴任したことかな、と思います。科学者・工学者の方と間近で接していただけるようになったことが、とても重要でした。こちらに来て間もない頃、有田先生の研究室にお邪魔させていただいたとき、先生が、ご著書の『人工生命』(医学出版・2000年)をくださったのがとても嬉しかったのを覚えています。文理融合という環境が、自分の研究を進めていくうえでの確信を与えたくれたような気がします [注6]。それから、亡くなられてしまいましたけれども、当時茂登山(清文)先生がいらっしゃって、すでに現代芸術をメインに教育研究活動をされていたことも、いま振り返ると大きかったと思います。またちょうどその頃、茂登山先生が名古屋港でアートセンターの運営をされていて、そこをメイン会場に、アジアで初めての「電子芸術国際会議(ISEAKB)」(2002年)を開こうというところだったのも、タイミング的にはよかったのだと思います。世界のメディアアートが名古屋に集結するという感じで、そこでたくさんのメディアアート作品や関係者の方に会うことができました。わたし自身は運営にはそれほど関わってはいませんでしたが、展示についてのレビューを書けと言われていたので、すべてというわけにはいきませんでしたが、いろんな作品を見ることになりました。とてもいい機会でした。
高校生へのメッセージ
Q:では最後に、おすすめの本をお願いします。
A:先ほどお話しのなかで挙げました『近代の藝術論』(山﨑編・中央公論社)は、古いんですけど、高校生にはおすすめかな、と思います。現在どうか、というよりも、そもそも芸術とはどういうものだったのか、という原点みたいなものがわかるという点で、よいのでは、と。先端のアートをやっている方から見れば、保守、反動みたいに見えると思いますが、まあ、それは仕方ないとして。
高校生の方へのメッセージとしては、あくまでわたしの経験からなのですが、「学校の外に出てみること」をお勧めしたいと思います。学校の外と言っても、そんなに特別な場所ではありません。わたしの時代には、街の楽器屋さんとか、放送局のようなメディアとか、そういうところでやっているイベントなどに行くことで、いろんな出会いがありました。いまはインターネットのおかげでもっといろんな出会いがあるでしょうけれども、街中にある身近なアートセンター(名古屋市で言えば、港区にある「MAT Nagoya」など)に顔を出してみると、アーティストだけでなく、まちづくりをやっている人や、いろんな年代の方々に会うことができて、面白いですよ。そこから将来自分にとって大事なことが見えてくるかもしれません。
注
- このときもし研究者の方に出会っていたら、きっと同じような衝撃を受けたと思います。なんて自由な人たちなんだ、と。
- 美術についても同じで、岡山市に県立美術館ができたのは、1988年、昭和の最後の年=わたしが大学を卒業する年でした。わたしが中高生の頃は、百貨店の美術フロアか、天神山にある文化センター(1962年オープン、前川國男設計によるモダニズム建築です。当時は図書館としての印象が強かったです)の展示フロアくらいしか、美術展ができるところはなかったように思います。その代わり、倉敷には大原美術館がありましたから、絵を見たいときはそちらに行ってました。ちなみに岡山市には他に、林原美術館や岡山県庁など、前川國男関連の建築がいくつかあります。文化センターは、その後、建築だけでなく立地や景観も含めてその価値が見直され、天神山文化プラザとして2005年に再出発しています。
- ひとつ引用してみます。「こういう時代に生きて、なおもだれよりも自己表現を宿命づけられている芸術家は不幸だといわなければならない。現実そのものが大声で叫びだしている環境のなかで、芸術家は自己を表現するためにますます大声をあげなければならない。更に彼は自分の声をどの方向に向かって発するか、すなわちだれの声に対峙して発すればよいのかがわからなくなっているからである」(山崎正和「情報化時代の人間」『劇的なる日本人』(1971)、引用は『高等学校 新撰 現代国語 二 三訂版』商学図書, 1982, pp.162-172, p.168)。デュシャンについては、次のように言われています。「デュシャンの「泉」をいわゆる現代芸術の先駆とみる説があるが、どうみてもこれは近代芸術の終点を示す作品でしかない。なぜなら、社会の中心をなすような情報体系(文化伝統)が相対化されて、それに対する反逆がむしろ無意味になったのが現代の特色だからである」(引用は同じく、『高等学校 新撰 現代国語 二 三訂版』商学図書, 1982, pp.162-172, p.170」。
- だからと言って、現実世界での犯罪行為を勧めているわけではもちろんありません。念のため。
- 人文系の研究者がなぜか共有している、科学に対する嫌悪感みたいなものからの抵抗を受けることもしばしばありました。「ソーカル事件」(1995年)があったせいかもしれません。またそれとは少し違いますが、新しい分野を研究しようとすることに対する権威の側からの反発も今から35年前にはまだありました(自分が認めていない分野の研究をさせない教員とか)。
- そういう環境にわたしを放り込んで、自由に活動させてくださった米山優先生に、あらためて深く感謝申し上げたいと思います。米山先生ご自身も、文理融合を強く意識されたご研究をされていました。