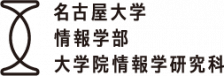石井 敬子先生 インタビュー 日本人は明るい声で「まずい」と言われると反応が遅れがち!?
聞き手:関 浩之
人生を決定づけた指導教官との出会い
Qこの特集は、高校生、受験生へ先生方の本音・本気の応援メッセージを送ることを目的としています。先生が大学に入ってよかったと実感したことは何ですか?
A 実家を離れ寮生活をしていましたが、圧倒的に自由で、好きなことに打ち込むことができたのはよかったと思います。
Q 中高時代の出会い、大学以降の出会いについてお話頂けますか。
A 中高時代は、その目の前にあった東京ドームに片足を突っ込んでいたぐらいその某球団のある選手を応援していました。野球との出会いは父の影響を受けて、もっと小さい頃にさかのぼるので、中高時代の出会いとは言えませんが、ただそのかつての情熱が無駄にはならず、野球を題材とした文化比較研究に携わり、少し前にその論文[1]が公刊されたので、案外いいこともあるんだという感じです。
大学で専攻した内容を職に活かすことができたらと思っていましたが、高校時代、漠然とした意味での「社会性」に関心があり、そこから社会性昆虫のことが気になったり、今から思えば全然方向が異なりますが精神科医に憧れを感じたりしていました。ただ、大学受験は、勉強不足と認識の甘さでうまくはいかず、結果的に京都大学農学部に合格しましたが、当時は大学入試の段階で学科まで決まってしまい、第1志望だった昆虫のできる農林生物学科からは漏れ、それとは異なる学科に進むことになりました。もうこの段階で、教免をとって、得意科目だった数学か化学の高校教員になろうと思い、せいぜい社会性に関連しそうな教養の授業をいろいろとることにしました。
そのうちの1つが社会・文化心理学に関するもので、結果的に私の指導教官となる先生の授業でした。そこで、ものの見方、特に言語の用法に関して、自分が当たり前だと思っていたことが他の社会・文化では全く当たり前ではないことを知り、衝撃でした。ある意味、私は自分が生まれ育ってきた閉鎖的な環境から逃げ出したく、実家から離れた京都に行ったものの、しかしその環境こそが自分を作り上げてものの見方をある意味規定している事実は、その自分を取り巻いてきたしがらみに対して関心を向けるきっかけになりました。当時、京大総合人間学部はできたばかりで、先生が研究の手伝いを求めていたのですが、そのような関心も相まって、他学部ながら手伝うことになりました。研究というのを知ったのはそれが初めてだったのですが、個人的にはとてもおもしろく、それを続けてみたいと思い、転学部することになりました。そして今に至るわけです。ですから、このような指導教官との出会いが私の人生を大きく変えたと思います。
Q 研究テーマを選ぶきっかけがドラマチックで、また「自分で行動を起こす」ことが後悔せずに生きるためにどれだけ重要なのか、よくわかりました。先生が選ばれた京大総合人間学部は当時開設されたばかりで活気があったことと思います。私も名大情報学部とその前に勤務していた大学の開設に関わったのですが、新しい学校や学部には志の高い学生が集まることを実感しています。それから、先生は学科にこだわらず興味のある授業をたくさん受けたとのことですが、私たちの情報学部も文理融合をキーワードにしており、低学年での専門基礎科目群は3学科共通で受講できますね。これらの科目は在校生にとても評判がよいと聞いています。
スランプから抜け出すコツ
Q さて、研究と受験勉強とは同じではないですが、どちらも長距離走のような面もあり、努力してもなかなか結果に現れないこともあります。そのようなときにどのように対処されていますか。
A 野球での例えになりますが、超一流のバッターであっても時としてスランプはあり、でもよほどでない限りベンチには下げられず、そんなときでも打席は回ってきます。研究者の場合、自分で勝手にベンチに下がったり休養をとったりすることはできるのですが、それでも野球選手を見習い、どんなときでも自分を信じて打席に立ち、バットを振り続けていくことが対処法として重要であると考えます。
Q 受験勉強で成績が上がらないときも同じ忍耐が必要ですね。
A ただ、結果が伴わないことの理由として、例えば新しい知識に自分が追いつくことができていないからいいアイディアが出せない、大学院生を含めた研究チーム内で研究の進め方に関して相互理解が進んでいない等の実質的な事柄が関与していることも往々にしてあります。そういうときはベンチに下がって、一歩引いた視点から内省し、何が問題でどういった対処が可能なのかを考えるようにしています。
Q 受験勉強で言えば、長期休暇のときに夜型から朝型に切り替えてみる、定評ある基礎問題集に立ち返ってみるとか、自分の不得意科目を得意とする友人に勉強の仕方を率直に尋ねてみるとか。
文化比較実験で苦労すること
Q 先生は文化の洋の東西を意識された国際共同研究をなさっています。異なる文化的背景をもつ被験者に対して実験を行って類似点や相違点を明らかにするというのは、言うは易く行うは難し、と想像します。苦労話からお話し頂けますか。
A ご質問の通り、文化比較研究の難しいところは、特に言葉を用いる限り、そもそもその語彙がその文化にあるのかどうか、語彙があったとしてもその意味やニュアンスが文化間で同じかどうかといった点です。このあたりが統制されていないと、実際に文化間で参加者の反応に差があったとしても、その差が一体何によって生じたのか解釈が難しくなります。そもそも実験研究の場合、文化差があると予測される点を要因(条件)として落とし込む必要があるため、その段階でまず単純化しなければなりません。さらに文化比較に関するそのような難しさを考慮すると、極力、言語情報は使わない形で単純化させていくことが望ましいと言えます。
Q 試験管の中で調べたい物質の量を正確に変化させ、他の全部の条件を厳密に同じにして行う比較実験を、被験者(人間)に対して行う必要があるので、まず「他の全条件を同一にする」ということ自体がとても難しいのですね。
A ただそうすると、実験の題材は、日常の文脈から切り離された人工的なものになってしまいがちで、それはそれで文化差が見出されたとしても、いったいその差が何を意味しているのか解釈が難しくなります。まとめると、単純化と非日常のバランスをとりつつ、予測に見合った適切な題材を見つけることが研究を行う上でのカギとなります。
Q まさにin vitro(試験管内、人工的状況)とin vivo(現実世界)とのせめぎ合いですね。
日本人が声の調子に引っ張られやすい傾向を示せた!
A 大学院生の頃、感情的発話の理解に関する文化比較研究を行っていました。これまで指摘されていたコミュニケーションの洋の東西の差を踏まえると、英語を母国語としている人々(例えばアメリカ人)は言語内容を重視しやすいのに対し、日本語を母国語としている人々はパラ言語を重視しやすいという予測が成り立ちました。
Q パラ言語というのは、人間がコミュニケーションにおいて使う言葉以外の手段のことでしょうか?
A そうです。言語情報のうち、イントネーションやポーズといった周辺的なものを指しています。その予測を調べるために、意味の快・不快と声の調子の快・不快を日本語と英語で作成し、日本人とアメリカ人の反応を比べました。
簡単そうに思えますが、まずは日米で意味の良し悪しの評定に関する調査を実施し、日米で同程度に評定されたいくつもの単語を候補にしました。次に日米の男女のバイリンガルをトレーニングし、その選択された単語を快い声の調子、または不快な声の調子で読んでもらいました。快い(不快な)単語は快い(不快な)声の調子が一般的ですが、実験刺激ですから、快い単語を不快な声の調子で読む、またその逆の不快な単語を快い声の調子で読むというのも必要で、トレーニングしてもこの録音の段階で時間がかかりました。
Q 明るい声で「まずい」と発話する練習をバイリンガルの話者に行ってもらう訳ですね。
A この段階で刺激は360個ありました。さらにこの刺激にフィルターをかけて、意味の情報をわからなくさせた上で、日米の参加者に呈示して声の調子の良し悪しを評定してもらいました。そして日米で同程度に声の良し悪しが評定され、かつ意味の良し悪しの評定値と声の調子の良し悪しの評定値が同程度になるような刺激セットを選ぶことにしました。結構厳しい基準ですが、こうしないと、作成した発話に対する反応に文化差が得られたとしても、それは刺激に問題があったと解釈されてしまいます。最終的に残った刺激は32個でした。
Q 日本語と比べて、英語は感情を出す程度が強く、おおげさな感じがします。そこを合わせないといけないから、候補刺激は最初の10分の1以下に絞らざるを得なかったのですね。苦労の連続ですね。
A また、ちょうどこの研究をしていたとき、フィリピンの研究者が滞在しており、フィリピンでは母国語のタガログ語に加えて、英語も学校教育で用いられており、それらのバイリンガルが多いことから、タガログ語と英語の刺激も同じ要領で作成することになりました。ただこのような刺激作成に至るまでに紆余曲折があり、大学院時代は刺激作成に翻弄されましたが、しっかりした実験刺激を作成したこともあり、予測と一致した結果が得られました。日本人は、アメリカ人と比べて、声の調子の快・不快を無視しなければならないのについそれに引っ張られてしまい反応が遅れてしまうといった結果でした。またフィリピンでは言語にかかわらず、日本人と同様に声の調子に引っ張られやすい、つまりパラ言語を重視したコミュニケーション様式に基づく反応が見られました。言語と文化が人々の認知にどのような影響を与えるのかに関して一石を投じる知見ともいえ、その結果、心理学分野におけるトップジャーナルに論文[2]が掲載され、苦労が報われました。
Q 鋭い着想が粘り強い実験を通じて見事に結実したのですね。私の前任校にもフィリピンからの留学生がかなりいて、同国人同士で会話をしているのを聞くと英語からタガログ語、そしてまた英語へとスイッチを繰り返すのです。「何で?」と聞いたら、「相手が言語をスイッチすると無意識に自分も追随してしまう」と言っていました。そのときはとても不思議に思ったのですが、今のお話(フィリピンではタガログ語、英語にかかわらずコミュニケーション様式に基づく反応が一定)をうかがって、少し腑に落ちたと感じました。(このお話は論文[3]でより詳しく紹介されています。)
Q いくつかの国では、西欧流の論理の流れを簡潔に表現して専門書を自国語に翻訳するのが難しいと聞くことがあります。これはその国の言語が劣っているということではなく、その国、あるいは民族固有の文化や思考様式に言語が寄り沿っているためかと思います。日本が明治維新の時、海外の文化・技術・論理を受容できるように日本語を「近代化」できたことは幸運でしたが、それにより何かが失われたのかもしれないと考えると複雑な気持ちになります。このような点について、何かお考えはありますか。
A 難しい質問ですが、1つ明らかなのは、文化は時とともに変容します。その一方で変わらないところもあるように思います(ご質問の文脈に関連した個人的な感想を挙げれば、夏目漱石の「私の個人主義」を読むと、同時代に生きていない私ですらその漱石の主張は痛いほど理解できるわけです)。何が変容し、何が変わらないのか、そしてその変わりやすさ・変わりにくさの差異は何が決めるのか(どうしてそのような差異が生じるのか)というのは、極めて重要な問題であり、研究領域を超えてその解決に向けて取り組む必要があるとさえ思います。
最後に
Q ご自分の大学生活で何か後悔していることはありますか?
A もっと読書をしておくべきでした。大学生の頃、沢木耕太郎が好きで、「深夜特急」をはじめとして当時出版されていたものはほぼ読み、また沢木耕太郎が卒論の題材にしたカミュもかなり読んで・・・といった感じで、節操もなく手当たり次第だったせいか、「何か偏っていたなあ、いわゆる古典の素養がないなあ」と痛感することが多々あります。
Q 先生にとっての「特別な1冊の本」を挙げてくださいますか?
A 「深夜特急」やカミュ「ペスト」もいいのですが、特別な1冊の本を挙げるとしたら、中島敦「李陵・山月記」(岩波文庫)です。「李陵」の司馬遷にはグッときますが、個人的には「名人伝」が好きですね。主人公の紀昌というのは、私が思う研究者の究極的な形で、絶対にたどり着けない境地に達しています。ただあれはアルツハイマーだと言ってしまえばそれまでで、何というか紙一重だなあと思います。
Q 理想は無限遠点にあり、でしょうか。今日はありがとうございました。
参考文献
[1] Chuang, R., Ishii, K., Kim, H. S., & Sherman, D. K. (2022). Swinging for the fences vs. advancing the runner: Culture, motivation, and strategic decision making. Social Psychological and Personality Science, 13, 91-101.
[2] Ishii, K., Reyes, J. A., & Kitayama, S. (2003). Spontaneous attention to word content versus emotional tone: Differences among three cultures. Psychological Science, 14, 39-46.
[3] 石井,北山.(2004). コミュニケーション様式と情報処理様式の対応関係:文化的視点による実証研究のレビュー,社会心理学研究 19(3), 241-254.