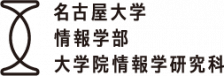特集「新型コロナと情報」:今こそ芸術の意味を考え直す
危機の時代?
ほんの少し前、「AIの時代に芸術家は生き残れるのか?」が問われていました。いま問われているのは、「コロナ禍で芸術家は生き残れるのか?」です。技術と自然の双方が、芸術家を脅かしているのです。もちろん、二つの問いは、その性格を異にします。AI時代に…の方は、芸術家の創造性はAIで代替されるのではないか、という問いでした。それゆえ、いやそんなことはない、創造性こそ人間の最後の砦だ、何よりも、人にはAIでは絶対に代替できない身体性がある。そんな強弁がまだ可能なように見えました。
しかし今回は、その最後の拠り所である身体性が問われているのです。音楽や演劇といった上演芸術の基礎にあるばかりか、人が生きていくのに欠かせない「息をすること(呼吸)」と「触れ合うこと(接触)」を制限された上で、それでもこれまで通りの仕方で芸術活動を続けることができるのか、と。
芸術の危機ではない
しかしこれは、芸術家の危機であって、芸術の危機ではないと思います[1]。理由はいくつかあります。
第一に、上演芸術を含めた伝統芸術は、人が呼吸し触れ合うことをやめられないのと同じで、必ず生き延びるからです。歴史が証明しているとおりです。感染の危険がおさまれば、どのように長い時間をかけても復活すると思います。
第二に、コロナ禍の影響をそれほど受けていない芸術ジャンルもあると思われるからです。たとえば映画芸術のうち、配信という形態を受け入れているものや、コンピュータベースのものについては、大きな打撃を受けてはいないかもしれません。
そして第三に、芸術にとって、技術の変化も自然の変化もほんらい脅威ではないはずだからです。この第三の点について、以下、少し詳しく説明します。
芸術は技術と自然観(生命観)の変化とともに変わる
芸術の古典的定義をひとつあげてみます。それは、芸術を、「技術でありながら自然であるかのように見える」もの、としています[2]。技術の産物なのにまるで生きているかのように感じられるもの、それが芸術だ、と言った方がわかりやすいかもしれません。
私たちが、マティアス・グリューネヴァルト作《イーゼンハイム祭壇画》(1512-16)のような作品に高い芸術的価値を認めるのも、優れた絵画技術により描き出されたキリストがあたかもそこで生きて病に苦しんでいるように見えるからです。ゆえにそれは、ペストなどに苦しむ人々に、癒しを与えることができたのでしょう。
https://en.wikipedia.org/wiki/Isenheim_Altarpiece#/media/File:Grunewald_Isenheim1.jpg
しかし芸術が、技術でありながら自然や生命を感じさせるものであるなら、新しい技術と新しい自然観・生命観は、新しい芸術を生み出すはずです。先端技術と自然の見方の変化は、ある種の芸術家にとっては脅威かもしれませんが、芸術そのものにとって脅威にはならないはずなのです。
実際、今から100年前、現在のコロナ禍と同じく、スペイン風邪と呼ばれた自然の猛威が大戦とならんで多くの人命を奪い、人々の自然観・生命観を大きく変えていくちょうどその頃、ロシアや欧州では、ダダ(1916)、シュプレマティズム(1916)、デ・ステイル(1917)、バウハウス(1919)、構成主義(1920頃)などの新しい芸術運動が次々と生まれ、その影響は、米国はもとより日本までをも含む広範な地域に波及していきました。
特にリシツキーらの構成主義は、当時最新の写真技術やタイポグラフィー技術を用い、新たな社会にふさわしい、生命感溢れる表現をもたらしました。しかもそれは、モビリティを欠く絵画ではなく、ポスターや広告など、街全体を芸術の舞台に変えることができ、しかも世界のあらゆる場所に比較的容易に運ばれうる新しい情報メディアの上に、構成的手法によって実現されたのです。構成主義の出発点となったマレーヴィチのシュプレマティズムは、キュビスムでさえそこから抜け出せなかった現実の目に見える自然の模倣を脱し、「もっとも原初的な状態から世界を構成」した点において、現在の人工生命研究にまで繋がるような新しい芸術でした [3][4]。
技術と自然、その両方の変化と対峙し、自らも変化してこそ、それは芸術と呼ばれるにふさわしいのです。どんな危機的状況に見えても、新しい技術を通して新しい表現を生み、人々に生きる力を与える。あるいは、自然とは何か、生命とは何かを問いかけることができる。そこにこそ、芸術の意味があるはずです。
〈死なない〉と語った人物への再注目
こうしたことを考えたとき、多くの人がいまあらためて、荒川修作(1936-2010)とそのパートナーであったマドリン・ギンズ(1941-2014)に注目しているのは、当然かもしれません。二人は、岐阜県養老郡養老町にある《養老天命反転地》(1995)などで知られています。
http://www.architectural-body.com/?p=389
なぜ彼らの名が語られるのでしょうか。それは、2020年5月が荒川の死後ちょうど10年にあたるからというだけではありません。世界がパンデミックと死の恐怖に怯えるなか、多くの人が、「死を約束された人間の宿命を反転」[5]させることを目指した彼らの姿を思い出したからだと思います。
荒川と親交の深かった馬場駿吉先生によれば、荒川とギンズの言う「天命反転」とは、「適切な着地点(ランディング・サイト)に生命あるいは人間の限りない創造性を有形物(建築的身体)として外在化させ、それを第三者が体験し、身体に転写することによって継代」[6]していくこととされます。有形物に外在化された生命がそれを体験する第三者の身体に転写され継代されていくかぎり、その生命は、〈死なない〉と言うのです[7]。この着地点すなわち〈降り立つ場=ランディング・サイト〉が、たとえば先に挙げた《養老天命反転地》でした。
ただしそこにあるのは、すでに見知った自然を模倣して外在化された生命ではありませんでした。荒川自身次のように言っています。人々はランディング・サイトで、〈身体の新しい行為や動きによって生まれる、全く新しい感覚を見つけ出〉さなければならない。そして、そのようにして見つけ出された新しい〈現象や事実を、私たち人間の世界で通用させる〉ために、〈新しいコモンセンス、道徳、倫理〉、そして〈制度の改革〉[8] へと向かうべきである。そのためには膨大な数の人間が一挙にこの変化を経験しなければならない、と。
新しいランディング・サイトの創出へ
したがって、このランディングが、荒川とギンズにより作られた場の経験でなければ起こらないとか、継代は人間身体のあいだだけでしか起こらないのだと考えるなら、それはひどく狭隘な、おそらく荒川とギンズの意図にも反する立場にとどまることになります。彼らが身体へのノスタルジーから思い起こされているだけなら、不幸であるとさえ言えるでしょう。二人にとって重要なのは、すでに述べたように、まだ誰も知ることのない生命性を外在化する仕組みをつくれるかどうか、人々がそこでまったく新しい感覚を見つけ出せるかどうかだからです。
このとき、生身の生命だけが生命ではない、現実の生命を包む、もっと大きな生命の枠組みを考えよう、意識が憑依するとんでもない機械もあるはずだ[9]、という言葉は、とても勇気を与えてくれます。
情報技術はすでにインターネットという場を遍在させています。またそれは、あらゆるスケールで実空間と連動しています。その全体がほんとうに新たなランディング・サイトになることができるなら、すなわち新しい生命性が外在化された場所になるなら、人々はとてつもなく大きな変化を経験することになるでしょう[10]。その創出のためにはしかし、情報技術についての正しい知識とそれを使いこなせる能力が必要です。
今こそ考え直すべき芸術の意味
バブル期以降、20世紀末からこれまでの数十年にわたって、芸術が主として経済的価値ではかられてきたことは、ご存じのことと思います。話題になるのは、どの展覧会が多くの人を集めたか、どの作品が高値で落札されたのか、どのアートフェスティバルが大きな経済効果をあげ地域の活性化に貢献したのか。そればかりでした。
もちろん、経済的自立は必要です。けれどもそれが、芸術にとって何が重要かを見えなくしてはいけません。先に述べた、芸術ほんらいの意味—どんな危機的状況に見えても、新しい技術を通して新しい表現を生み、生命とは何かを問いかける—が見直されるべきだと思います。
かつてわたしは、愛知万博(愛・地球博)と重なる時期に開かれた荒川修作の展覧会レビューにこう書きました。
「『自然との共生』をテーマとした万博関連企画のうち、『底なし』の生命と宇宙を前提とし、今ある人間の姿を変えてもいいから〈生きろ〉と呼びかけているのは、〔荒川+ギンズの〕《志段味循環型モデル住宅》以外にない。」[11]
わたしたちを変え、変化する自然と共生していくために、情報技術を用いた新しいランディング・サイトをつくってみたい。情報学部でそんな方に出会えれば、と思っています。長文失礼いたしました。
注
[1] 芸術家の経済的危機をどう救うかは真剣に考えなければなりませんが、別問題です。
[2] Kant 1790.
[3] シュプレマティズム(マレーヴィチ)と構成論的手法、ならびに人工生命研究との関連については、 有田2012を参照。「もっとも原初的な状態から世界を構成」も同書からの引用(p.194)ロシア・アヴァンギャルド全体、ならびにその政治的悲劇については亀山1996。
[4] 寺山編2005
[5] 馬場2016, p.126. この節の引用はすべて馬場2016から。荒川自身の言葉は〈 〉で記した。
[6] 馬場2016, p.136
[7] あわせて、こうした反転の意図への批判があったことも想起すべき。雨宮1996, 岡崎1996, 郡司1996など。
[8] 馬場2016, p.92
[9] 池上+石黒2016, p.249, 有田2012も参照。ただしこのような発言が許されるのは、その人がほんものの科学者である場合だけです。
[10] それはネット上にかつての芸術作品を流通させることや、すでにある芸術の形態を不完全なかたちでネット上に再現することでもないでしょう。もちろん、プロパガンダなどではありえません。
[11] 秋庭2005, p.197. 今振り返ると、他にもあったような気がしますが…。
文献
秋庭史典(2005)「「荒川修作を解読する」展レビュー」『美術手帖』864, 196-197
雨宮民雄(1996)「空の眼差しと形の呪縛—荒川/ギンズ批判」『現代思想』24(10)「総特集 荒川修作+マドリン・ギンズ」, 83-95
有田隆也(2012)『生物から生命へ—共進化で読みとく』ちくま新書
池上高志+石黒浩(2016)『人間と機械のあいだ—心はどこにあるのか』講談社
岡崎乾二郎(1996)「ゼロのポレミーク」『現代思想』24(10)「総特集 荒川修作+マドリン・ギンズ」, 360-366
亀山郁夫(1996)『ロシア・アヴァンギャルド』岩波新書
郡司ペギオー幸夫(1996)「「何ものも」得ず、「志し」をもたず」『現代思想』24(10)「総特集 荒川修作+マドリン・ギンズ」, 411-421
寺山祐策編(2005)『エル・リシツキー—構成者のヴィジョン』武蔵野美術大学出版局
馬場駿吉(2016)『意味の彼方へ—荒川修作に寄り添って』書肆山田
Kant, I. (1790), Kritik der Urteilskraft
名古屋大学情報学部・大学院情報学研究科
社会情報学専攻(情報哲学講座)准教授 秋庭史典
専門領域:美学・芸術学