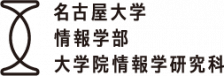特集「新型コロナと情報」:感染症、道徳、情報技術
新型コロナウィルスの流行は人間の心の様々な脆さを露呈させました。「何々が不足するかもしれない」という情報によって不安を掻き立てられた多くの人が大量の買いだめに走りました。移動や営業の自粛が要請される中、人々は互いの行動を監視し合い、他県ナンバーの自動車や営業している店に危害が加えられました。イギリスなどでは5Gの電波が感染症を悪化させるという噂がひろまり、通信施設が放火されるという事件も多発しました。感染者を特定して誹謗中傷あるいは脅迫する人々、医療従事者など感染のリスクの高い状況に置かれた人々を差別する人々がいます。「夜の街」という言葉で特定の職業に対する差別や偏見が助長されており、ヨーロッパやアメリカではアジア人に対する差別や暴力も起こっています。新型コロナウィルスは確かに深刻な脅威ですが、こういった行動は明らかに過剰に思われます。なぜこんなことが起るのでしょうか。そして私たちは(とりわけ情報学に従事する人間として)この状況をどのように受け止めて、どう対処するべきなのでしょうか。簡単な答えはありませんが、本稿ではこういった問題に取り組むための足掛かりとなるラフな考察を提示したいと思います。
人類史における感染症
文明の誕生以来、人間社会は常に様々な感染症に悩まされてきました。現代の日本に生きる私たちにはおそらくその深刻さは想像が難しいでしょう。感染症が人間集団にとって深刻な脅威になったのは定住生活と農業を始めてからのことです。メソポタミアで人々が定住と小規模な農業を始めてから大規模な国家が形成されるまでにはおよそ4000年以上の時間がかかっていますが、この間に多くの社会が感染症によって崩壊したと考えられています(スコット、2019)。
ある程度の規模の国家が形成されると、集団として感染症に対する適応が生じます(病原体が人間集団に適応するとも言えます)。感染症に対して抵抗力のある遺伝子が選択されると同時に、病原体の方もそれほど破壊的でない系統がその社会の中で生き残ります。依然として今の基準から見れば少なくない人が、集団に定着した感染症で命を落としはするのですが、最初の時ほどの猛威を振るうことはなくなっていきます。
しかしこのように感染症の「飼い慣らし」に成功した集団が、感染症を経験していない集団と接触すると、後者の集団は著しいダメージを被ることがしばしばでした。ユーラシア大陸の東西両端のイギリスと日本は、感染症を飼い慣らすために必要な規模の人口を持った社会が成立するのが遅かったので、大陸から持ち込まれる感染症に長い間繰り返し悩まされました。感染症とのファーストコンタクトの最も劇的な例の一つは16世紀のアメリカ大陸での感染でしょう。この時、ヨーロッパから持ち込まれた天然痘、はしか、ジフテリア、おたふく風邪などによって、ごく短い時間で南北アメリカ大陸の人口が激減し、そこにあった数々の文明が崩壊しました。人間の歴史は、感染症の伝播と集団的な適応を獲得していく過程の繰り返しという観点から描写することができます(マクニール、2007)。
近年、先進国においては、公衆衛生と医療の発展、特に様々なワクチンや抗生物質の開発によって感染症の脅威は著しく低減しました。1980年にはWHOが天然痘の根絶宣言を出し、人間は史上初めて世界的に蔓延した深刻な感染症の一つを撲滅することに成功しました。医療のますますの発展によって、その他の感染症も撲滅することができ、人類はやがては感染症に悩まされることがなくなるかもしれない。そんな期待も当時は抱かれました。しかしながら天然痘の根絶という福音が届いたのとほとんど同時に、エイズやエボラという治療も予防も難しい新たな感染症が現れました。その後もSARS、新型インフルエンザ、MERSなど新しい感染症が次々に現れ、従来の感染症の中にも、抗生物質やワクチンなどに対する抵抗力を持った新しい系統が生まれています。人類と感染症の戦いは、少なくとも当分の間は、終わりそうにありません。してみると新型コロナウィルスの流行も、人類と感染症との長い戦いの中の新しい一つのエピソードなのでしょう。
感染症が人間の心理や行動に与える影響
このように人類は有史以来、恒常的に感染症の脅威に曝されてきました。そのためか感染症に対する恐怖は深いところで人間の心理や行動に影響を与えています(マコーリフ、2017、第11章)。虫やネズミ、排泄物や体液や傷口や内臓、配偶者以外との性交、悪臭や汚れ、異質な集団に属する人間などに対して人間が反射的に抱く嫌悪感や、そういったものを忌むべきものと見なす慣習は、人間と感染症との戦いの歴史を反映していると考える研究者もいます。
そして嫌悪は道徳的判断や政治的傾向に影響を与えることが、様々な実験によって示唆されています。事前に何らかの仕方で嫌悪感を刺激された被験者、あるいは感染症について考えさせられた被験者は、そうでない被験者よりも、古くからある道徳観や保守的な政策を支持する傾向を持つことが示されました(同上)。具体的に言うと、実験条件に置かれた人々は、より集団主義的になり、よそ者に対する偏見を強め、同性愛や人工中絶に強く反対しました。また彼らは社会規範に違反する人間に対してより厳しい態度を見せました。新型コロナウィルスが流行している時に、不倫関係にある相手とトイレで性行為に及んでいたことを報じられた芸能人は、人々の嫌悪感や反感を刺激する要因をフルハウスで揃えていたわけです。
道徳的政治的傾向には顕著な地域差がありますが、これにも感染症が関係しているのかもしれません。感染症の地理的歴史的データと、道徳的政治的傾向についての国際的なデータを対照した研究によって、感染症の脅威がより大きな地域(インド、アフリカ、中国など)では、人々がより集団主義的であることが分かりました(マコーリフ、2017、第12章)。アメリカ国内で比較した調査でも同様の結果が得られました(南部の方が集団主義的で、感染症のプレッシャーが強い)。
集団主義とは、個人の意思や自由よりも自分が属する集団の規範や秩序を優先し、また自分が属する集団を他の集団よりも重視する考え方のことです。それに対して個人主義とは、すべての個人に平等の権利を認め、個人の自律的な決定権を尊重する考え方です(ここで言う「個人主義」は、自分さえ良ければ良いという「利己主義」とは異なります)。もちろん集団主義か個人主義かというのは、宗教や経済や産業や周りの国々との関係など、様々な要因によって影響を受けるでしょう。しかしその他の様々な要因の影響を考慮しても、やはり感染症のプレッシャーは集団主義的傾向のはっきりした目印になるという調査結果が出ました。
これは感染症のプレッシャーが人々をより集団主義にするということを意味するのでしょうか。確実なことは分かりませんが、一つの可能な説明は、感染症のプレッシャーの強い地域では、できるだけよそ者と接触しない方がリスクを避けられるために、排他的な考え方が発達して、集団主義的になっていった、というものです。もちろんこれは仮説にすぎず、それを実証するのは困難でしょう。しかし感染症のことを考えさせることが、人々の集団主義的な傾向を強めるという上記の実験結果や、現在私たちが痛感しているように、感染症に対する有効な対策(移動や経済活動の制限、人々の行動の記録の収集など)が、個人主義と折り合いが悪いものであるという事実は、この仮説のもっともらしさを高めます。
してみると新型コロナウィルスの流行下において人々が見せた過剰な行動の数々も、感染症と人類の長い付き合いの中で発達してきた心理的メカニズムと慣習の故なのかもしれません。
ミームと病原体
近代以前は基本的にどのコミュニティも集団主義的な傾向を強く持っていたでしょう。個人主義的な考えは、ルネサンス期の人文主義、宗教改革、啓蒙主義、ロマン主義などの思想や文芸の運動、そして様々な分野の近代化とともに徐々に拡がっていったものです。人間は少しずつ個人の自由を増大させ、部族主義・自民族中心主義を希薄化し、因習的な権威から解放され、他集団への差別を抑制し、多様性への寛容さを育ててきました(もちろん到底十分とは言えず、いくらかましになったという程度ですが)。このことは経済や産業、そして科学技術の飛躍的な発展と無関係ではないでしょう。個人の経済活動が活発になることで、貨幣や財がより円滑に流通し、経済と産業が活性化します。また人々が自由に考え、話し、行き来することで知識やアイディアの交換もより活発になり、新しい発見やイノベーションが生まれやすくなります(リドレー、2010)。集団の境界をまたいだ協力が広がることで、異なる集団間の協力関係、依存関係が生まれ、排他的な集団主義が一層鳴りを潜めます。このような集団主義の縮小と、協力による利益の増大のフィードバックループによって、人間は次第に個人の自由を広げると同時に、協力できる集団の輪を広げたのだと考えられます(ピンカー、2015)。
進化生物学者心理学者【谷村省吾先生からご指摘を受けて打ち間違いを訂正しました。谷村先生ありがとうございます。2020年7月12日】のリチャード・ドーキンスは、価値のあるアイディアの創造と流通を「ミームmeme」という概念を使って説明しました(ドーキンス、2006)。「ミーム」はドーキンスの造語で、「遺伝子」を意味する「gene」と「模倣する」を意味する「mimic」などの言葉に基づいています。ドーキンスは人々の間で伝播するアイディアや情報をミームと呼び、それが遺伝子と同様の複製、変異、選択の過程を経て進化する、と論じました。つまりミームは人間から人間に伝達され(複製)、改良されたり他のミームと組み合わされたりすることで新しいミームが生まれ(変異)、より有益なミームが世代を超えて継承される(選択)、ということです。言葉、技術、科学的知識、芸術、慣習、社会制度、規範、宗教、儀礼などなどは全てミームです。だとすると文明の発展とはミームの進化(あるいはミームと人間の共進化)そのものだ、と言えるでしょう。
ミームという概念を使うと私たちは、感染症に関する問題を次のように表現することができます。ミームが進化しやすい環境は感染症が広がりやすい環境でもある、と。なぜならミームも病原体も人間によって運ばれ、人間から人間へと伝播するからです。都市への人口集中、都市から都市への人間の移動はミームにも病原体にもありがたい状況です。地理学者のジャレド・ダイアモンドは、ユーラシア大陸で最も早く高度な科学技術や統治体制が発達したのは、多くの文明が活発に交流を行ない、技術や知識を交換し合っていたからだ、と論じます(ダイアモンド、2012)。しかしそのためにユーラシア大陸は慢性的に感染症を抱え、そして頻繁に破滅的な流行に襲われていました。一方でアメリカ大陸では、ヨーロッパ人が16世紀に様々な感染症を持ち込むまでは、それほど感染症に苦しんでいた様子は見られません(マクニール、2007)。もっとも彼らが感染症に苦しんでいなかったということが、ヨーロッパ人との最初の接触があれほど悲劇的な結果を引き起こした主たる原因になったのは皮肉なことですが。
要するに歴史的に見れば、ミームを進化させることと、感染症を抑えることはトレードオフの関係(あちらを立てればこちらが立たず、の関係)にあったということです。
情報技術の役割
新型コロナウィルスの流行、特に近年、感染症に深刻に悩まされることが少なくなったヨーロッパやアメリカの先進国で猛威を振るったことは、改めてローカルな集団の境界をまたいで移動すること、そして見知らぬ他者と接触することのリスクを浮き彫りにしました。ここにおいて情報技術の役割は以前にもまして重要になります。
情報技術の発展はミームの進化と感染症の抑制のトレードオフの関係を変化させます。文字が発明されたとき、すでに人間と人間の直接的なコンタクトはミームの伝播にとって必須の条件ではなくなりました。とはいえ文字で伝えられる情報は、量の点でも種類の点でも、非常に限定されたものでした。18世紀以降、情報技術は飛躍的に進歩して、多種多様な情報が情報技術を介して素早くやりとりされるようになりました。次々に生まれる新しいコミュニケーション手段、それを支える通信インフラ、情報を保存する媒体の進歩によって、私たちは直接的なコンタクトなしに膨大な情報をやり取りすることができるようになっています。さらに人工知能の技術はそれらの膨大な情報の海の中に私たちが溺れてしまわないよう、重要な情報、価値のある情報を効率的に利用することを助けてくれます。
ただしここには、これらの技術をうまく制御し活用することができれば、という留保をつける必要があります。というのも、情報技術の発展によって可能になる大量の情報の高速な流通や拡散、人工知能を使った情報の抽出・自動フィルタリングは様々な弊害を生み出してもいます(例えばパリサー、2012;笹原、2018;オニール、2017)。要は人間にとって有益であるがゆえに生き残るミームもあれば、人間に害を与えているにも関わらず生き残る「寄生的」なミームもある、ということです(久木田、2020)。
また情報技術がどれほど発達しても、リアルタイムの対面コミュニケーションには、こういった情報技術を介したコミュニケーションでは代替できない側面もあります。リアルタイムの対面コミュニケーションでは、互いの表情、声のトーン、ジェスチャー、匂い、身体的な接触なども使ってコミュニケーションをしており、こういった要素は相手との間の相互理解、信頼、共感、愛着を強めたり、相手から協力を引き出したり、相手と交渉をしたりする際に重要です(ウォレス、2018)。それゆえ情報技術に対する過度の依存は、共感する能力を失わせて、人と人との繋がりを弱めるものだと警告する人々もいます(例えばタークル、2017)。他方、テレロボティクスやVRなどは、人間同士のコミュニケーションのレパートリーを増やし、人間関係を一層豊かにするポテンシャルを持つものでもあります(吉藤、2017;ベイレンソン、2018)。
情報技術の発展に伴って、人間のコミュニケーションのあり方は大きく変化してきました。そして大きな変化が起こるときには、新しい技術への懸念や批判も付きまといます。ソクラテスは対話を重視したために書物を嫌いましたし、印刷技術が現れた時にはキリスト教の僧侶やは「手書きの写本でなければ聖書の神聖さが失われる」と批判しました。コミュニケーションにおける最初の大きな変化は、人類の祖先が、話し言葉を使うようになったときに起こったことでしょう。動物行動学者の岡ノ谷一夫や認知考古学者のスティーヴン・ミズンは、人間の言語は音楽から発展したのではないか、と考えています(岡ノ谷、2016;ミズン、2006)。だとすれば現在のような言語に移行したとき、人類の祖先は感情を伝達する非常に強力な手段を失ったのかもしれません。音楽から言葉への移行期には、上の世代は「最近の若者は言葉ばかりに頼って、歌を歌わない。あんなことでは本当に心の通じ合うコミュニケーションは取れない」などと言ったかもしれません。
私は、だから現在の変化も憂慮する必要がない、と言いたいわけではありません。現在の情報技術の発展とそれにともなうコミュニケーションの変化は本当に深いところで人間同士の関係や社会の在り方を変化させるでしょう。それによって失われるものも決して少なくないと思います。懸念するべきことはたくさんあるし、場合によっては規制をかける必要もあるでしょう。とはいえ私たちが慣れ親しんだコミュニケーションの在り方も情報技術の発展史の一段階のものであり、それが絶対に最善と考える理由もないと思います。人間の心理や感情、社会の慣習や規範、コミュニケーションの価値、そして新しい技術の特性を踏まえて、今後のコミュニケーションとそれに基づく人間と社会のあるべき姿を構想し設計することが必要です。これは、そもそも私たち情報学研究科のメンバーの重要なミッションの一つであったわけですが、新型コロナウィルスの流行はそのミッションの重要性をますます高めています。
参考文献
- ジェレミー・ベイレンソン(2018)、『VRは脳をどう変える変えるか――仮想現実の心理学』、倉田幸信訳、文藝春秋。
- リチャード・ドーキンス(2006)、『利己的な遺伝子<増補新装版>』、日高敏隆、岸由二、羽田節子、垂水雄二訳、紀伊国屋書店。
- ジャレド・ダイアモンド(2012)、『銃・病原菌・鉄――1万3000年にわたる人類史の謎』(上・下)、倉骨彰訳、草思社。
- 久木田水生(2020)、「人工知能と人間のよりよい共生のために」、『RAD-IT21 WEBマガジン』。
- キャスリン・マコーリフ(2017)、『心を操る寄生生物――感情から文化・社会まで』、西田美緒子訳、インターシフト。
- ウィリアム・H・マクニール(2007)、『疫病と世界史』(上・下)、佐々木昭夫訳、中央公論新社。
- スティーヴン・ミズン(2006)、『歌うネアンデルタール――音楽と言語から見るヒトの進化』、熊谷淳子訳、早川書房。
- 岡ノ谷一夫(2016)、『さえずり言語起源論 新版 小鳥の歌からヒトの言葉へ』、岩波書店。
- キャシー・オニール(2018)、『あなたを支配し社会を破壊するAI・ビッグデータの罠』、久保尚子訳、インターシフト。
- イーライ・パリサー(2012)、『閉じこもるインターネット――グーグル・パーソナライズ・民主主義』、井口耕二訳、早川書房。
- スティーブン・ピンカー(2015)、『暴力の人類史』(上・下)、生島幸子・塩原通緒訳、青土社。
- マット・リドレー(2010)、『繁栄――明日を切り拓くための人類10万年史』(上・下)、大田直子、鍛原多惠子、柴田裕之訳、早川書房。
- 笹原和俊(2018)、『フェイクニュースを科学する――拡散するデマ、陰謀論、プロパガンダのしくみ』、化学同人。
- ジェームズ・C・スコット(2019)、『反穀物の人類史――国家誕生のディープヒストリー』、立木勝訳、みすず書房。
- シェリー・タークル(2017)、『一緒にいてもスマホ――SNSとFTF』、日暮雅道訳、青土社。
- パトリシア・ウォレス(2018)、『新版 インターネットの心理学』、川浦康至・和田正人・堀正訳、NTT出版。
- 吉藤健太朗(2017)、『「孤独」は消せる。』、サンマーク出版。
久木田水生
名古屋大学 大学院情報学研究科 社会情報学専攻 准教授
情報技術と人間と社会について哲学的・倫理学的観点から考えている。
ウェブページ